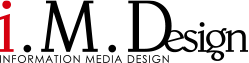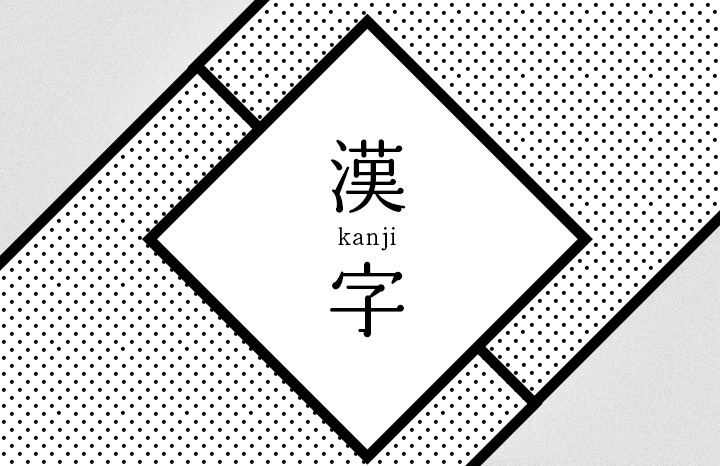リーダーやマネジメントを任されたら、読んでほしい5冊のビジネス書
2016.06.10
ビジネス

「ゆとり世代、平成チルドレン、26歳北摂ガール」(北摂っていうのは大阪の北部を指します。)
そんな私がマネジメントを経験する際に参考にした書籍たちをご紹介。
これからマネジメントを経験するであろう人。
または、「将来人の上に立つ人間になりたい!」って方にもおすすめのビジネス書です。
以下、ご紹介する順番ごとに読んでもらえると「スッ」と自分のなかに入ってくるのでどうぞ。
目次
1冊目:99%の人がしていないたった1%の仕事のコツ
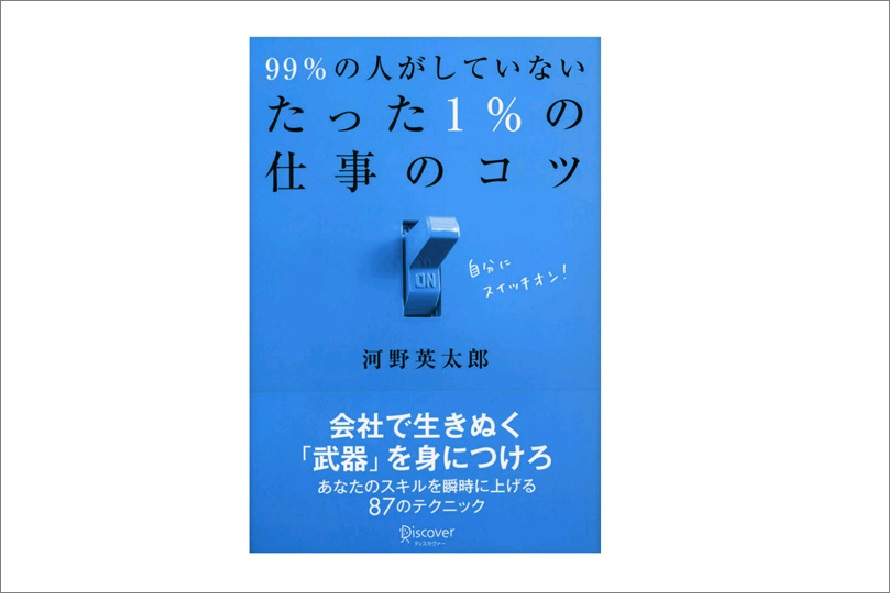
著者:河野英太郎
「8つのコツ」で分けられていて、
状況に合わせて、必要なところを読み返すこともできる。
特に7つ目のコツは必読。
≪おすすめポイント≫
伝え方一つで仕事の効率が変わるってことを実感。
結構、当たり前のようなことが書いてあるんだけれども、「やっぱりそれ大事だよね…」と再認識させてくれる。
コレを読んで効率があがり、本格的にマネジメントに携わるようになったなぁ…。
この本は他シリーズもあり、
99%の人がしていなかったたった1%のリーダーのコツ
99%の人がしていない たった1%のリーダーのコツ
これも合わせて読むのもおすすめ。
2冊目:リーダーは「時間の使い方」が9割!
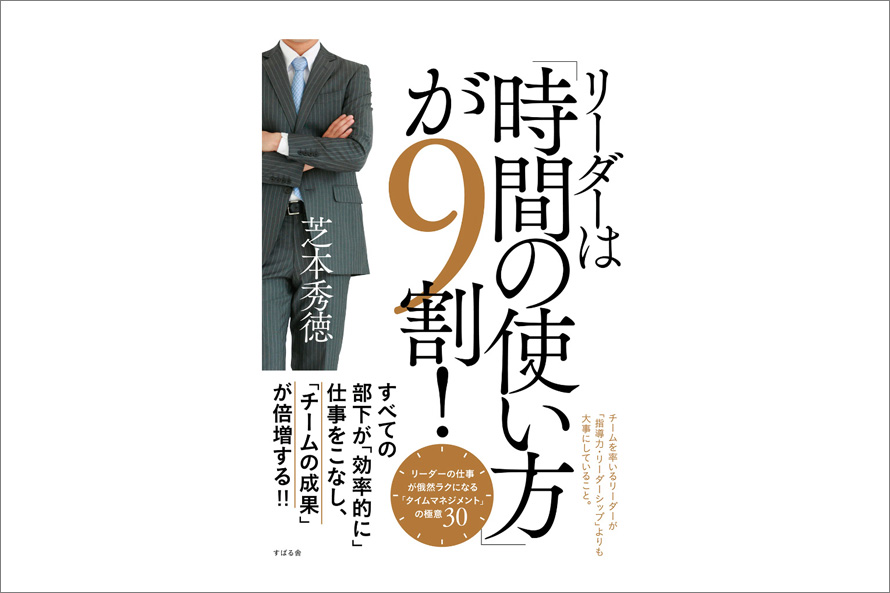
著者:茂本秀徳
珍しい横書きスタイル。
文字数もそんなに多くなくて、すらすら~と読めちゃう。
”立場・役割にあった時間の使い方”なので、プロジェクトが始まる前やスケジュールを立てるときに参考にするとよし。
≪おすすめポイント≫
「モチベーションが上がる!」というような啓発的な内容ではなく、実用的な内容。
文字だけでなく、タイムスケジュールの見本なども文面の合間に出てくるので、簡単にマネすることができる。
3冊目:「ついていきたい」と思われるリーダーになる51の言葉
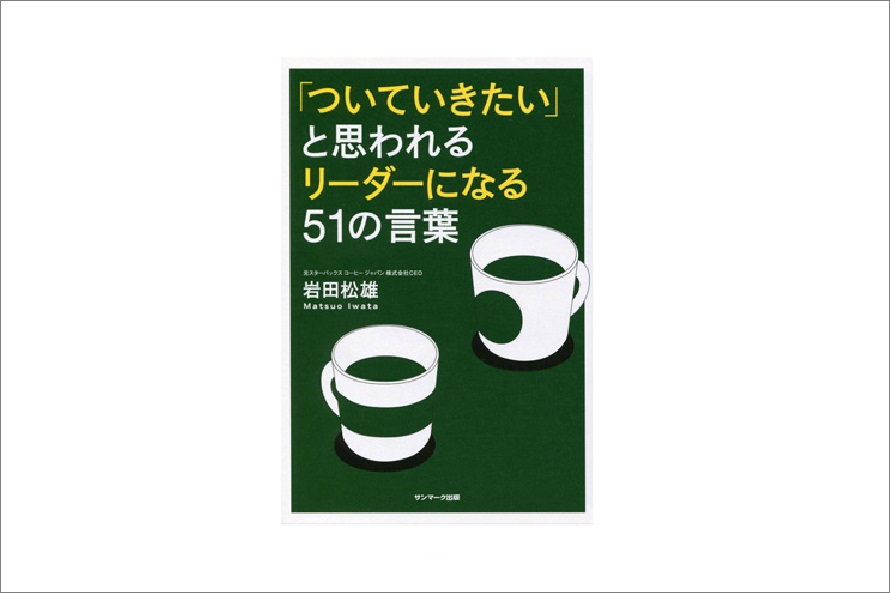
著者:岩田松雄
言霊ってことばを信じているので、こういうタイトルに弱くて読破。
(過去には『20代で使ってはいけない100の言葉』という本のシリーズも読んじゃうほど弱い。)
“まずは形から。””尊敬される上司でいたい。”
こんなふうに本当は思ってる人、たくさんいますよね?!そんな素敵な方に是非。
(…私はそう思ってた。)
≪おすすめポイント≫
具体的な仕事の進め方は、この前に紹介した本で学んで、この本では”考え方”を学ぶことができる。
また、いいことだけでなく、上に立つ立場の孤独な面も書いてあるところが共感でき、気持ち的に救われる。
あとはモチベーションを上げるのにもってこい。
4冊目:”困った職場”を劇的に変える 話し合う技術を磨く
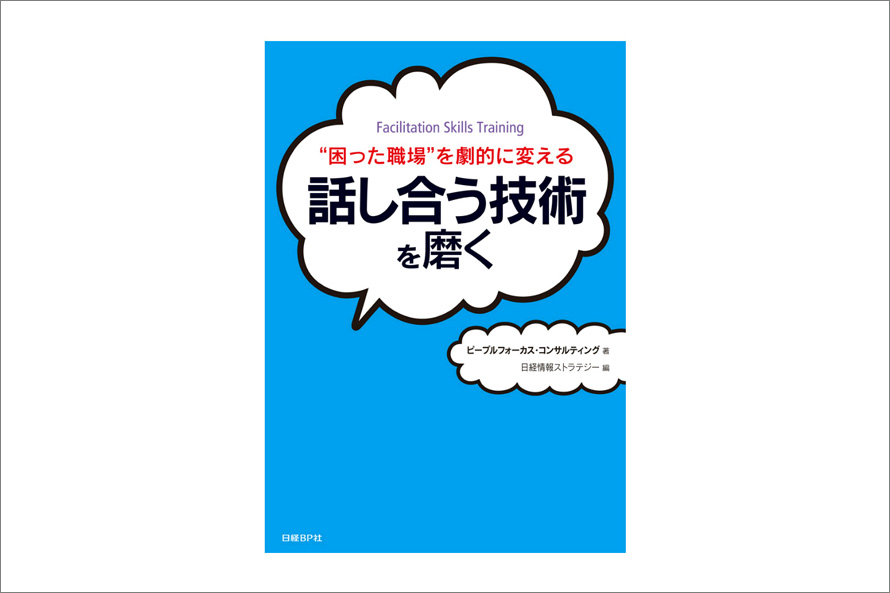
著者:ピープルフォーカス・コンサルティング
編集:日経情報ストラテジー
リーダーやマネジメントを行う立場になると、必ずといっていいほど直面するのが会議の進め方。
“メンバーから意見がでない””自分だけが話す会議になる”
こんな悩みをスッキリさせてくれる方法がたくさん。
≪おすすめポイント≫
この本を参考にミーティングを行うと、メンバーの意見を聞くことができ、コミュニケーションや相談連絡の頻度が向上。
結果、プロジェクトの進捗状況なども漏れなく把握することができ、先手先手の行動が可能になるのでほんと大助かり!
5冊目:ワクワクする職場をつくる。
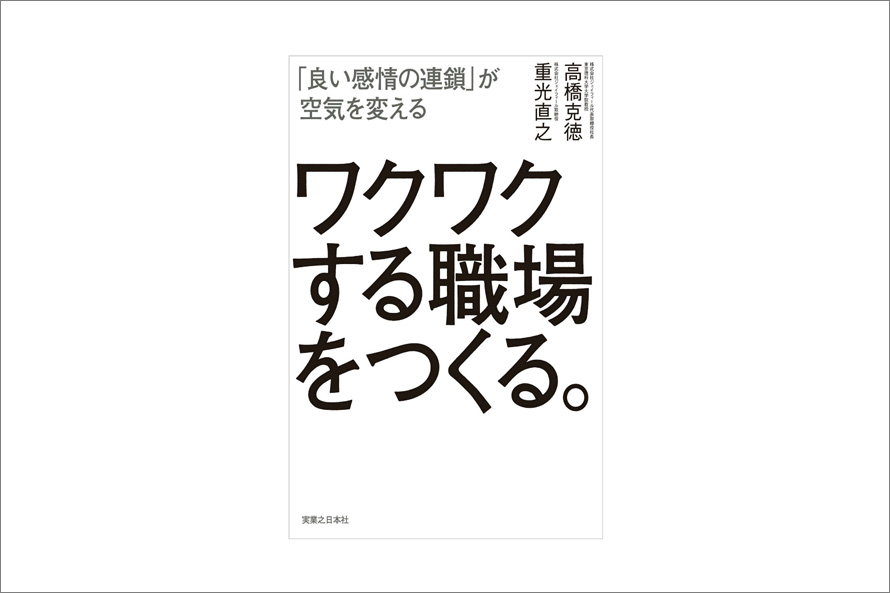
著者:高橋克徳/重光直之
プロジェクトなど進めていく中で
「チームの一体感がうまく作れない、メンバーの志気が下がっている」
と感じたときに参考にしてほしい。
≪おすすめポイント≫
タイトルは”職場”という大きい括りなっていて「間違ったかな?!」と思ったけど、文章での場面が「あるある」と納得できることが多かった。
実際に今いるチームで考えたときにすごくしっくりきて、一つの行動を実践するだけで、雰囲気が変わった。
”楽しく仕事がしたい”という願いを叶える方法が書いてある1冊。
番外編:マンガで簡単に読めるビジネス書
▼マンガでやさしくわかるアドラー心理学
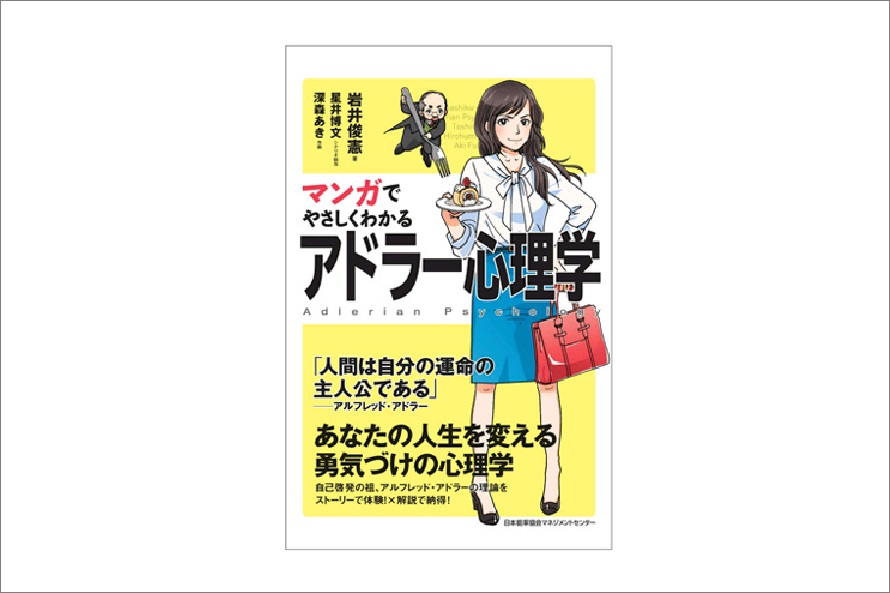
仕事がうまくいかないときや職場での人間関係で悩んだときなどにどうぞ。
▼マンガでよくわかるディズニーのすごい仕組み
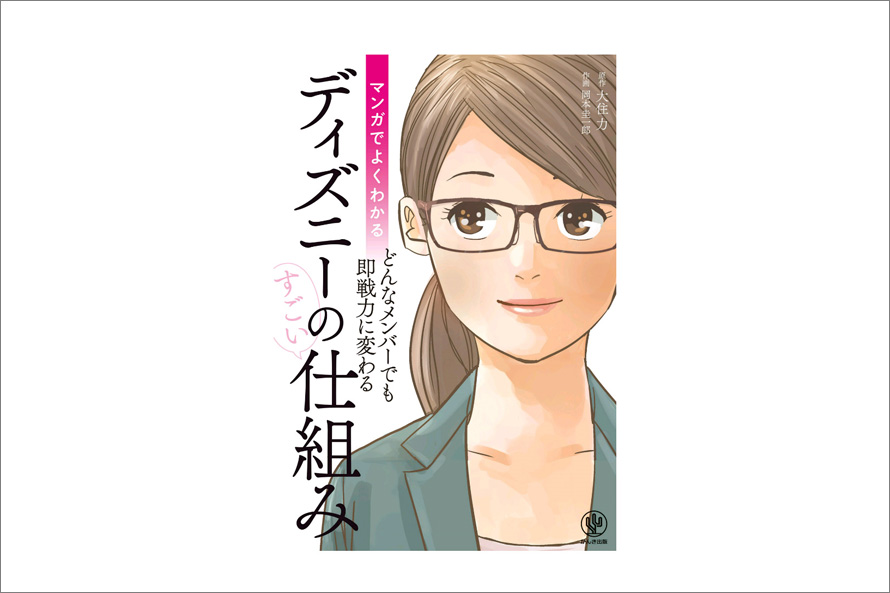
ディズニーというブランド名にただただ惹かれて読んでみたのですが、とても参考になる内容で大満足。
メンバーを指揮する方法がたくさん書いてあるので、
「部下のやる気が…」
と悩んでいる人はどうぞ。
何するでも真似から入る私にとって、ビジネス書はなくてはならない存在。
特に今回紹介した順番に読むことで、自分の中で知識のステップアップできてより身に付きやすい。
ちなみに、本は基本的にAmazon.co.jp:Kindle ストアでの購入が中心。
電子書籍はスマホがあれば、”好きな場所で、好きな時間(トキ)に、読みたい本が読める”ってとこが良いかな。
わたし的には、暗い部屋でも読めて、そのまま寝落ちできるところがポイント高い!
(目には良くないので、その辺は自己責任でお願いします。)
ではまた!